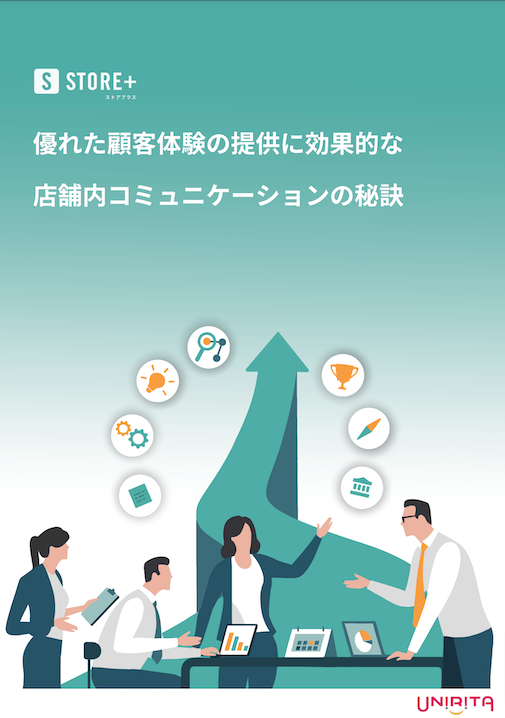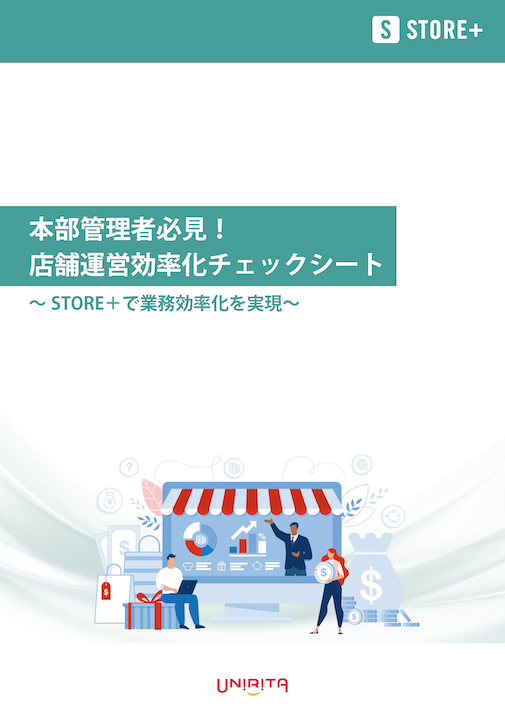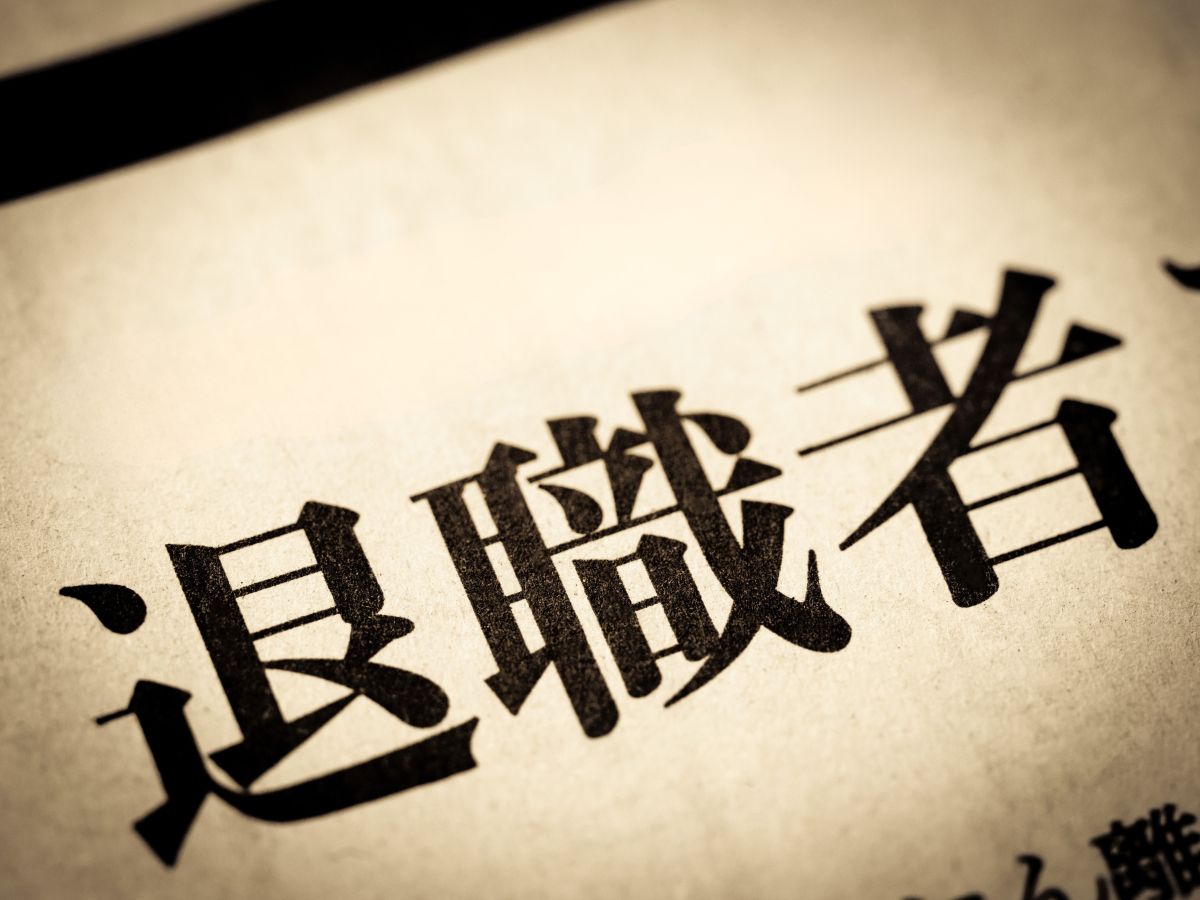短期間で即戦力化!多店舗展開企業のための標準化されたオンボーディングマニュアル作成法

多店舗展開を進める卸売・小売業の企業にとって、人材育成は事業成長において重要な課題の一つです。店舗数が増えるにつれて、「店長など教育担当者の業務負担が増す」「店舗ごとに指導内容やサービス品質に差が出る」「結果として新人の即戦力化に時間がかかる」といった構造的な課題を抱えていませんでしょうか。
本記事では、これらの課題を解決に導く「標準化されたオンボーディングマニュアル」の作成法を、具体的な手順に沿って解説します。本部が主導となってマニュアルを整備し、全店舗の新人スタッフのスキルと意識を短期間で高いレベルに引き上げるための実践的なノウハウをご紹介します。このマニュアルを活用することで、教育の効率性を高め、安定した店舗運営を実現しましょう。
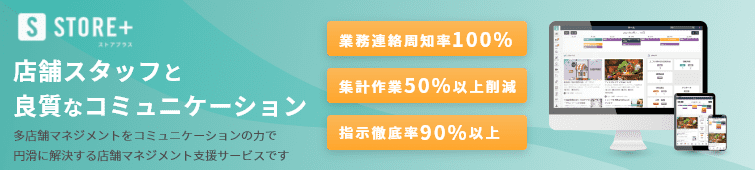
多店舗展開企業におけるオンボーディングの重要性
多店舗展開を行う企業にとって、新しい店舗が増え、売上規模が拡大していくことは喜ばしい成長の証です。しかし、成長に伴い、各店舗の「人」に依存する部分、特に新人スタッフの教育と育成、つまり「オンボーディング」が企業全体のサービス品質や運営効率を大きく左右する要因となってきます。店舗運営部門のご担当者さまが日々感じているであろう、教育に関する構造的な課題から見ていきましょう。
多店舗運営における人材教育の現状と課題
多店舗展開を行う小売・卸売業の現場では、人材育成において本部が想定する理想と、現場が直面する現実との間に、大きな隔たりが生じがちです。
店舗間で教育内容に差が出る理由
本部が「全店舗で統一された最高のサービスを提供したい」と考えていても、実際には店舗ごとに教育の質に大きなばらつきが生じています。その最大の原因は、教育が「人」に依存している、つまり「属人化」している点にあります。
具体的には、新人スタッフへの指導は、多くの場合、店長やベテランスタッフに一任されています。優秀な店長やスタッフがいる店舗では、その人の経験や熱意に基づいた質の高い教育が行われる一方で、経験の浅い店長や指導に不慣れなスタッフのみの店舗では、指導内容が不十分になることや、指導の順序が場当たり的になりやすいです。
マニュアルがあっても形骸化することや、情報が古くなることで、指導者が「マニュアルにないけれど、私のやり方はこうだ」と独自の解釈を加えてしまい、結果的に店舗間のサービスレベルに差が生まれるのです。例えば、商品の陳列ルール、お客さまへの声かけのタイミング、クレーム対応の初期対応など、統一されるべき基本動作が店舗によって異なる状態は、お客さまの企業に対する印象を損なうことにつながります。
この「教育の属人化」は、店舗運営の再現性を阻害し、特定店舗の成功体験を他の店舗へ水平展開することを困難にしています。
新人定着率の低下がもたらす損失
教育内容のばらつきや不十分さは、新人スタッフの定着率にも深刻な影響を与えます。指導が不十分だと、新人は「何を期待されているのかわからない」「自分の仕事が正しいのか不安になる」といった状態で放置されがちです。特に、初めての接客業務などにおいて、自信を持って行動できないことは、仕事へのモチベーションを著しく低下させます。
定着率の低下は、単に「人が辞めてしまう」という問題にとどまりません。企業にとって以下のような大きな損失をもたらします。
- 採用コストの増加
辞めた人員を補填するために、継続的に採用活動を行わねばならず、広告費や人件費が増大します。 - 教育コストの浪費
新人教育にかけた時間や人件費、そして備品などの費用が、スタッフの離職によって無駄になってしまいます。 - 組織全体の士気低下
人の入れ替わりが激しい店舗では、既存スタッフが「また新人が辞めるのか」という諦めや疲弊を感じ、職場全体の士気や生産性が低下します。
- これらの損失を避けるためにも、誰が指導しても一定の質を保てる、仕組み化された教育体制、すなわち「標準化されたオンボーディングマニュアル」が不可欠となります。
オンボーディングが果たす役割とは
「オンボーディング」とは、単なる「新人研修」を指す言葉ではありません。新しく組織に加わった人材が、組織の文化、ルール、業務内容を理解し、一人前の戦力としてスムーズに立ち上がり、定着するまでの一連のプロセス全体を指します。多店舗展開企業において、このオンボーディングプロセスを適切に設計することには、極めて大きな意味があります。
早期戦力化を支える育成設計の重要性
オンボーディングの最大の目標は、「早期の戦力化」です。単に仕事を教え込むのではなく、新人が自力で業務を遂行し、チームに貢献できる状態に持っていくことです。
これを実現する育成設計には、以下の要素が組み込まれている必要があります。
- 段階的な学習経路の提示
最初に何を覚え、次に何を習得し、いつまでにどのような状態になるべきか、明確なロードマップを提示します。これにより、新人は「いつ、何を頑張ればよいか」が明確になり、不安を感じることなく学習を進められます。 - スキル習得度の可視化
どこまで進捗したか、何ができるようになったかを客観的なチェックリストやテストで確認できるようにします。これにより、指導者は進捗状況を把握しやすくなり、新人も達成感を得やすくなります。 - 企業理念と行動規範の共有
技術的なスキルだけでなく、なぜこの仕事をするのか、どのような価値観でお客さまと接するのかといった「企業文化」の部分も初期段階で共有することで、単なる作業員ではなく、企業の「顔」としての意識を早期に芽生えさせます。
この育成設計を具体的に落とし込んだものが、標準化されたオンボーディングマニュアルとなるのです。
なぜマニュアルの標準化が必要なのか
店舗運営におけるさまざまな課題、特に「人材」と「サービス提供品質」に関する課題を根本的に解決する鍵は、教育の「標準化」にあります。標準化とは、バラバラだった教育手順や内容を、本部が定めた「全店舗で共通の、最も効率的で質の高い手順」に統一することです。
教育の属人化が引き起こす問題
標準化の対極にあるのが「教育の属人化」です。これは、特定の経験豊富な人材に教育の良し悪しが依存している状態を指します。
教育の属人化が店舗運営部門にもたらす具体的な弊害は、以下の通りです。
- サービス品質の波
特定の店舗やシフト帯において、教育が行き届いているスタッフとそうでないスタッフが存在し、お客さまが受けるサービスの質に差が出ます。一貫性のないサービスは、お客さまの企業ブランドに対する信頼を揺るがします。 - 指導者のモチベーション低下と疲弊
教育担当者である店長やベテランスタッフは、新人が入るたびにゼロから指導内容を考え、時間と労力を費やします。これは非常に大きな負担となり、本来の店長業務(売上管理や店舗戦略立案など)がおろそかになる原因となります。 - 情報のブラックボックス化
教育ノウハウが個人の頭の中に留まってしまうため、その指導者が異動や退職となると、それまでの質の高い教育ノウハウが失われてしまいます。
標準化による教育品質の均一化
教育の標準化は、これらの属人化の問題を解消する直接的な解決策です。標準化されたマニュアルを導入することで、以下の効果が得られます。
- 最低限の品質保証
マニュアルが「これだけは必ず教えるべきこと」と「この水準までは必ず到達させるべきこと」を明確に示すため、すべての店舗で最低限必要な教育が漏れなく実施されます。これにより、どの店舗に入った新人スタッフも、必ず企業が定める基本ラインに到達できます。 - 指導者の負担軽減と効率化
店長や指導スタッフは、マニュアルに沿って教えるだけでよくなります。指導内容を毎回考える必要がなくなり、教育の準備時間が大幅に削減されます。空いた時間を、新人の精神的なフォローアップや、より深い店舗戦略の指導に充てられるようになります。 - 本部による教育のコントロール
本部が作成、更新するマニュアルを共通の「教育の羅針盤」とすることで、本部が意図する経営方針や最新のサービス情報を、迅速かつ正確に全店舗のスタッフへ浸透させることが可能になります。
店舗運営の再現性を高める仕組みづくり
小売・卸売業における多店舗展開の成功は、「成功体験の再現性」にかかっています。A店の成功をB店、C店でも同じように実現できるかどうかです。教育の標準化は、この再現性を高めるための最も基礎的な仕組みとなります。
標準化されたマニュアルは、単なる業務手順書ではありません。それは、「この手順で、この意識で業務を行えば、必ず成果が出る」という成功法則を体系化したものです。
例えば、マニュアルに「お客さまとのアイコンタクトは3秒以上を心がける」「商品の欠品を発見したら即座に店長へ報告する」といった具体的な行動規範が明文化されていれば、すべての店舗のスタッフが同じ行動を取り、同じレベルの接客と店舗管理が実現します。この統一された行動様式こそが、お客さまに一貫したブランド体験を提供し、店舗運営の再現性を高めるのです。
この再現性が確立されることで、新しい店舗を出店する際の準備期間や、開店後の軌道に乗るまでの時間も短縮でき、企業全体の成長スピードが加速します。
オンボーディングマニュアル作成の基本ステップ
標準化されたオンボーディングマニュアルを作成するプロセスは、闇雲に手順書を書き出すことから始めるのではなく、現状の把握とゴール設定から逆算して進めることが肝要です。
ステップ1:現状課題の洗い出し
マニュアル作成の第一歩は、「いま、何が問題で、何を解決したいのか」を明確にすることです。店舗運営部門のご担当者さまは、以下の観点から現場の課題を洗い出してください。
- 新人が特に戸惑っている業務は何か?
例:レジ操作、在庫確認方法、特定商品の説明、クレーム対応の初期対応など。 - 店舗間で特にサービス品質のバラつきが出ている業務は何か?
例:商品の陳列基準、お客さまへの声かけのタイミング、開店・閉店作業のチェックリストなど。 - 教育担当者(店長など)が「教えるのが大変だ」と感じている部分はどこか?
教育担当者の負担が大きい部分は、マニュアル化の優先度が高いです。 - 過去のヒヤリハットやクレームに直結した人為的ミスは何か?
品質や安全に関わるミスを防ぐための手順は、最優先でマニュアル化すべき項目です。
これらの課題を、アンケートやヒアリングを通じて複数の店舗から集め、「解決すべき優先度の高い課題リスト」を作成します。このリストこそが、マニュアルに盛り込むべき核となる内容を決定する羅針盤になります。
ステップ2:業務フローの整理と優先度づけ
課題が明確になったら、新人スタッフが店舗で最初に行う業務から、徐々に難易度が上がる業務まで、すべての業務を漏れなく洗い出し、プロセス(フロー)として整理します。
- 業務の棚卸し
店頭での接客、バックヤードでの作業、清掃、商品の品出し、在庫管理など、店舗運営に関わるすべての作業をリストアップします。 - 難易度と重要度の分類
リストアップした業務を、「難易度(易しい・普通・難しい)」と「重要度(低・中・高)」で分類し、「難易度は易しく、重要度が高い」業務から優先的にマニュアル化します。
- 最優先: お客さまの安全に関わること(衛生管理など)
- 次点: 接客の基本手順、商品知識。
- 後回し: 店長の許可が必要な特殊な対応、高度な戦略的業務。
- 学習ロードマップの作成
整理した業務を、「入社1日目」「1週間目」「1カ月目」「3カ月目」といった具体的な期間で区切り、段階的に何を習得させるかをマッピングします。これにより、マニュアルの「目次」と「学習進捗管理表」が一体化します。
ステップ3:教育内容の標準フォーマット化
マニュアルの核となる具体的な指導内容を作成します。重要なのは、「誰が読んでも、誰が指導しても同じ解釈になる」ように表現を統一することです。
チェックリストや動画の活用
単なる文章での説明は、現場では「読まれないマニュアル」になりがちです。現場で使われるマニュアルにするためには、以下のフォーマットを積極的に活用します。
- チェックリスト形式の導入
- 「業務完了」のチェックリスト
例えば、「レジ締め手順」であれば、一連の作業を箇条書きにし、一つ一つの作業が終わるたびにチェックを入れられるようにします。これにより、新人も指導者も「どこまでやったか」「何が残っているか」が瞬時に把握でき、抜け漏れがなくなります。 - 目標達成型のチェックリスト
「レジ操作を1人で10回問題なくこなす」「3人のお客さまに商品の特徴を説明する」など、単なる「知識のインプット」ではなく「行動の達成」を目標にする項目を設けます。
- 「業務完了」のチェックリスト
- 動画コンテンツの活用
文字では伝わりにくい「動作」「姿勢」「表情」などは、短い動画(5分以内が理想)で補完します。特に、お客さまへのお辞儀の角度、商品の持ち方、笑顔の作り方、特定の機器の操作手順など、体で覚える必要がある部分は動画が非常に有効です。動画は「誰が見ても模範となる、本部が定めた正しいやり方」を収録することで、店舗ごとの指導のバラつきを確実に解消できます。
>>関連記事「動画共有によるスタッフの教育・研修がおすすめな理由」はこちら
ステップ4:現場スタッフの意見を反映させる
本部が机上で作成したマニュアルは、現場の実情と乖離していることが少なくありません。「現場で使えない」と判断されたマニュアルは、すぐに棚の奥にしまわれ、使われなくなってしまいます。これを防ぐため、必ず作成途中のマニュアルを現場の意見でブラッシュアップします。
- テスト店舗での試用
実際に教育担当者(店長など)と新人スタッフがいる数店舗を選定し、作成中のマニュアルを使用してもらいます。 - 意見収集の実施
- 指導者側
「この説明はわかりにくい」「この手順は現場では非効率だ」「教えるのに時間がかかりすぎる」といった、教える上での問題点をフィードバックしてもらいます。 - 新人側
「この言葉の意味がわからない」「この作業の目的が不明瞭だ」「マニュアルのどこに何が書いてあるか探せない」といった、学ぶ上での疑問や困難をフィードバックしてもらいます。
- 指導者側
これらの現場の声を反映させることで、マニュアルは「本部が作ったもの」から「現場で本当に役立つツール」へと進化し、現場スタッフの協力的な運用が期待できるようになります。
短期間で即戦力化を実現する工夫
マニュアルの整備はゴールではなく、「即戦力化」という結果を生み出すための手段です。作成したマニュアルを、新人が短期間で使いこなし、実務能力へ昇華させるための具体的な工夫が必要です。
初日から実践できるタスク設計
新人スタッフは、入社初日から「自分は役に立てるだろうか」という不安を抱いています。この不安を早期に解消し、仕事への意欲を高めるためには、すぐに現場で貢献できるタスクをマニュアルの冒頭に配置することが有効です。
- 「非接客」の簡単な業務から始める
例:商品の整理整頓、清掃(お客様の目につきにくい場所から)、備品の補充、期限チェックなど。
これらの業務は、特別なスキルを必要とせず、店舗の環境に慣れるための準備運動になります。 - 小さな成功体験を積み重ねる
初日に「店舗の役に立った」という実感を新人に与えることで、仕事への前向きな姿勢を育みます。指導担当者は、こうした小さなタスクの完了に対しても、積極的に褒める機会を設けましょう。 - 業務の「全体像」を最初に伝える
複雑な業務手順に入る前に、「この仕事が店舗運営全体の中でどんな意味を持つのか」という業務の目的を最初に説明します。目的がわかると、単なる作業ではなくなり、主体的に取り組む姿勢が生まれます。
「覚える」より「やってみる」学習法
小売・卸売業の業務は、知識を暗記することよりも、体を動かし、お客さまと接する中で「体験」として習得することが重要です。マニュアルは「読むもの」ではなく、「活用して行動するもの」として設計すべきです。
- 実践と反復練習を促す
マニュアルの各項目に、「この手順を○回繰り返すこと」「〇〇の状況を想定してロールプレイングを行うこと」といった、具体的な行動のノルマを設定します。
例:「クレーム対応の初期対応手順を、担当者と3回ロールプレイングし、チェックリストにチェックを入れる」 - OJT(On the Job Training:実地研修)をマニュアルに組み込む
マニュアルを読み終わってから現場に出るのではなく、マニュアルの「ステップ1:レジ操作の基本」を読んだら、すぐに指導者の監督下でレジ操作を数回行う、というサイクルを回します。座学(知識のインプット)とOJT(実践でのアウトプット)をセットにすることで、知識がすぐに技術として定着します。
視覚的に理解しやすいマニュアル構成
新人にとって、分厚い文字ばかりのマニュアルは、それだけで心理的な壁となります。マニュアルを「手に取りやすく」「読みやすく」「理解しやすい」構成にすることで、学習意欲を維持します。
- 配色とフォントの統一
企業ブランドカラーに沿った配色や、誰もが読みやすいフォントサイズ(例:11pt以上)と色(黒や濃紺)を使用します。重要事項は赤字や太字、囲み線などで強調し、どこを優先的に覚えるべきかが一目でわかるようにします。 - 図解や写真の多用
特に、商品の陳列、機械の操作、ユニフォームの着こなしなど、「どのようにすべきか」が重要な箇所には、必ず高解像度の写真やイラストを挿入します。写真には必ず短い説明文(キャプション)を添え、何の動作や手順を示しているのかを明確にします。 - 目次と索引の工夫
マニュアルが分厚くなる場合は、目的の情報をすぐに探せるよう、具体的なキーワードで検索できる索引を充実させます。また、目次も階層構造を明確にし、知りたい情報に最短で辿り着けるよう工夫します。
>> 関連記事「店舗従業員・本部社員のためのビジュアルコミュニケーション活用術」はこちら
メンター制度やロールプレイングの導入
マニュアルはあくまでツールであり、人を育てるのは人です。マニュアルに加えて、人的なサポート体制を導入することで、新人の定着率とスキル習熟度を一層高めます。
- メンター(指導役)制度の明確化
店長や教育担当者とは別に、新人の精神的なサポートや、日々の小さな疑問を気軽に聞ける「メンター」役を店舗ごとに任命します。メンターは年齢やキャリアが近いスタッフを充てることで、新人の心理的な壁を取り除き、職場への早期適応を促します。 - 実践的なロールプレイング
マニュアルに沿った接客トークやクレーム対応を、指導者やメンターと繰り返し演習します。この際、指導者は必ずフィードバックを行い、「どこが良かったか」「どこを改善すべきか」を具体的に伝えます。特に「お客さまから難しい質問をされたらどうするか」「想定外のクレーム対応」など、マニュアルだけでは対応が難しいケースをシミュレーションすることで、新人の対応力と自信を養います。
運用・改善フェーズで気をつけたいポイント
オンボーディングマニュアルは、「作って終わり」ではありません。現場で使われる中で必ず課題が見つかるため、継続的に「育てていく」視点が欠かせません。この運用・改善のサイクルこそが、マニュアルを常に「生きたツール」として機能させる鍵となります。
定期的な内容更新とフィードバックサイクル
小売・卸売業の現場は、取り扱う商品やキャンペーン、法規制などが常に変化しています。マニュアルの内容が古くなると、現場スタッフは「これは古い情報だ」と判断し、マニュアル全体への信頼を失いかねません。
- 責任者の明確化
マニュアル全体の「更新責任者」(本部内の特定の担当部署)を明確に定めます。この責任者が、内容の陳腐化を定期的にチェックする義務を負います。 - 更新の頻度とルール
業務の根幹に関わる部分(例:レジ操作、衛生基準)は年に一度、それ以外の部分(例:商品知識、キャンペーン関連)は半年に一度など、更新頻度を事前にルール化します。 - 変更点の通知
マニュアルを更新した際は、ただ差し替えるだけでなく、「いつ」「どこが」「なぜ」変わったのかを全店舗の店長や教育担当者に明確に通知します。変更点が分かりにくいと、古い情報で新人教育を続けてしまうリスクが生じます。
現場の声を吸い上げる仕組み
前述の通り、マニュアルは現場の視点を取り入れることで初めて価値を持ちます。本部主導の更新だけでなく、現場からのボトムアップの意見を積極的に吸い上げる仕組みが必要です。
- 「マニュアル改善提案制度」の設置
全スタッフが、マニュアル内の「分かりにくい点」「間違っている点」「追加すべき内容」を、本部へ気軽に提案できる窓口を設けます。提案が採用されたスタッフには、報奨や表彰を与えることで、現場スタッフのマニュアルへの関与意欲を高めます。 - 定例会議での意見交換
エリアマネージャー会議や店長会議などの定例会議の議題に、必ず「オンボーディングマニュアルの活用状況と課題」を組み込みます。現場の生の声、特に「新人がこの部分で必ずつまずく」といった具体的な課題を吸い上げます。 - 新人アンケートの実施
新人が入社後1カ月、3カ月などの節目に、「マニュアルは役に立ったか?」「特に分かりにくかった部分は?」といった質問を含むアンケートを実施します。実際にマニュアルを使って学んだ人の意見は、改善のヒントの宝庫です。
デジタル化による共有と管理の効率化
多店舗展開企業において、マニュアルを紙ベースで運用するのは非常に非効率です。内容の更新や共有、そして新人の学習進捗の管理を効率化するために、マニュアルのデジタル化は必須です。
- クラウドでの一元管理
マニュアルを社内ネットワークやクラウドサービスなどで一元管理します。これにより、全店舗が常に最新バージョンの情報を参照できるようになります。過去のバージョン管理も容易になり、誤った情報での教育を根本から防ぎます。 - 検索機能の強化
デジタル化の最大のメリットは「検索性」です。新人が「レジの返金手順が知りたい」と思ったとき、マニュアルのどこをめくるかを考えるのではなく、キーワード検索で瞬時に該当ページに辿り着けるようにします。 - 進捗管理の自動化
マニュアルに付随するチェックリストや理解度テストをデジタル化することで、本部や店長が「A店の新人Bさんは、どこまで学習が進んでいるか」「C店の新人Dさんは、まだこの重要な項目を終えていない」といった個人の進捗状況をリアルタイムで把握できます。進捗の遅れている新人や、教育が行き届いていない店舗を早期に発見し、適切なフォローアップを行うことが可能になります。
>>関連記事「企業や店舗の人材育成に欠かせないIT活用!IT教育を行うべき3つの理由」はこちら
まとめ:教育の属人化をなくし、全店舗で同じ成果を出すために
本記事では、多店舗展開を行う小売・卸売業の企業さまが、新人を短期間で即戦力化させるための「標準化されたオンボーディングマニュアル」作成法と、その運用・改善のポイントを詳細に解説してきました。
オンボーディングマニュアルがもたらす長期的効果
標準化されたマニュアルの導入は、一時的な教育効率の向上にとどまらず、企業全体に長期的なメリットをもたらします。
- 企業ブランド価値の向上
全店舗で均一で質の高いサービスが提供されることで、お客さまの信頼を獲得し、企業ブランドの価値が長期的に向上します。 - 組織の成長基盤の構築
誰が辞めても、誰が入ってきても、高いレベルで業務を教え、店舗運営を継続できる強固な仕組みができます。これは、今後の出店計画や事業拡大における大きな成長基盤となります。 - 店長や社員のエンゲージメント向上
教育の負担が軽減され、本来注力すべき店舗戦略や人材育成(モチベーション管理など)に時間を使えるようになるため、店長や社員の業務満足度(エンゲージメント)が高まり、離職率の低下にもつながります。
全店舗で育成の「共通言語」を持つことの価値
標準化されたオンボーディングマニュアルは、単なる紙やデータの塊ではありません。それは、全店舗で働くスタッフが「私たちの会社は、お客さまにこういう価値を提供し、そのためにこういう行動を重視する」という、仕事に対する共通認識を持つための「共通言語」となります。
店舗運営部門の皆さまには、この共通言語を本部主導で設計し、現場の知恵を借りながら磨き上げていくことが求められます。教育の属人化という壁を打ち破り、全店舗で高い品質を再現できる仕組みを構築し、企業全体の成長を加速させてください。
多店舗運営のオンボーディングに役立つツールのご紹介
多店舗管理ツール「STORE+(ストアプラス)」は、新人スタッフのオンボーディング(早期戦力化)を強力にサポートします。
本記事で解説した「標準化されたオンボーディングマニュアル」を、お知らせ機能を使って全店舗の新人スタッフに分かりやすく共有できます。また、動画配信機能を活用すれば、接客の模範動作や機器の操作手順など、文字だけでは伝わりにくい「実践的なスキル教育」を、全店舗で均一かつ効果的に行うことが可能です。
さらに、フォーム機能を使い、マニュアルに沿った習熟度チェックや理解度テスト、OJTの完了報告を各店舗からスムーズに集めることができます。こうした仕組みにより、本部担当者は新人スタッフ一人ひとりの学習進捗状況を効率的に把握し、遅れている店舗やスタッフへの迅速なフォローアップにつなげることができます。
オンボーディングの効率化と品質の標準化に課題をお持ちの店舗運営ご担当者さまは、ぜひ「STORE+」をご検討ください。
>>「STORE+(ストアプラス)」について詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 https://www.youtube.com/embed/xkyXF_9abME
https://www.youtube.com/embed/xkyXF_9abME

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。

執筆者情報:
ユニリタ STORE+チーム
株式会社ユニリタ ビジネスイノベーション部
多店舗管理ツール「STORE+」のプロモーション担当チームです。
コミュニケーション情報を蓄積・共有・活用するシステムに長年携わってきたメンバーが、多店舗・多拠点の管理に課題を持つ方に、役立つ情報をわかりやすく発信することを心がけています。